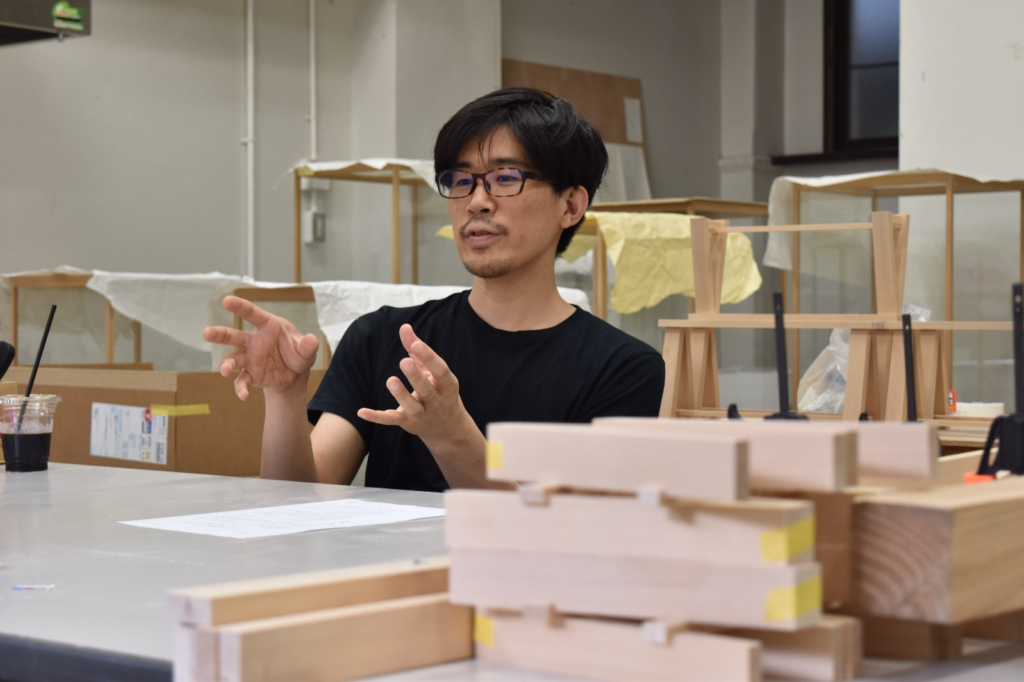
空間を利用し、音や光を用いた感覚的な作品を中心に発表し続ける久門剛史さん。京都市立芸術大学で彫刻を専攻したのち、京都を拠点に国内外の芸術祭や展覧会で精力的に活動しています。アジア回廊現代美術展では、元離宮二条城の東南隅櫓を舞台に大型の新作インスタレーションを展示中です。
今回は、新作と元離宮二条城という場所の持つ物語の関係性、そして、そこで使われる「音」と久門さんの関係性についてお話を伺いました。
新作について教えてください。二条城というと、非常に壮大で場所そのものの「物語性」が強いように思えます。一方で、久門さんの作品は繊細でどこか「身近さ」を感じさせます。制作のインスピレーションはどう掴まれましたか?
テレビでバラエティ番組を見ていて、急に画面の上に海外の事件の緊急速報が表示されることがあります。瞬時には理解できない次元のこと、だけど同じ地球上の出来事で、同じ時間軸の中で起こっているという情報が急に目の前に出てくる。つまり、自分が普通に生きたいと思っている生活のスピードとは、明らかに違う速さですごく大事なことが決断されていたり、起こっていたりする。東日本大震災の時、頻繁にテレビ画面の上部はスピードがありながらも重大な情報で占拠されていて、そういう中で自分の人生を改まって考えるようになった体験から、そういった事象のギャップを非常に感じるようになりました。
二条城を見たときに、やはり大政奉還という出来事が一種のアイコンになっていると感じました。ここで行われたのだ、何かしら決断がなされたのだ、と。
でもその大きな決断と同時に、僕のように生活をしていた普通の人たちは、重大な決断がされたという事実を知っていたのかと疑問に思いました。歴史では、その渦中にいる人がフィーチャーされがちですから。でも、庶民たちはどうしていたのだろう。
それは、気楽にバラエティ番組を見ていたら速報で悲しいことや大きな変化が突然やって来る、ということに似ているのではないかと思い、現代で生きる自分と歴史的建造物の間でシンクロしたように感じました。それが、作品の最初のインスピレーションになりました。

今回の作品の一階の部分は、「自分」の存在を意識することのできる極めて個人的な空間にしたかった。一方でそれとは異なる性質を持つ部分も同じ空間に存在させたかった。二つの要素を感じることはできるけど、全貌を一度に覗くことはできない。そのギャップや相互関係をテーマに、二条城東南隅櫓の全ての空間で光や音を使った作品にしたいと考えていました。

久門さんの作品にはたびたび大きな音や強い光が現れます。これらにはどういった効果があるのでしょうか?
僕は彫刻的に物事を考えるということに敬意を払っています。自分にとって、重い音や、強い光というのは物質として存在しているように思えます。
彫刻的な感じ方で音や光を考えるときは、徐々に現れるとか徐々に鳴るというより、「0か1か」という感じ方をしたいと思っています。例えば、石はドンとその場にある。小さい石でも凜としている。地面に落ちている木の枝もそこに在る。光も音もそうあって欲しいと考えています。

久門さんはチェルフィッチュ『部屋に流れる時間の旅』の舞台芸術とともに、音も担当されています。久門さんにとって「音」を作ることと、インスタレーション作品などを制作することには、何か違いを感じられていますか?
もともと音楽をやっていた4つ上の兄の影響で、音に興味を持つようになりました。彼が持って帰ってきたビーチボーイズの”ペットサウンズ”やフリッパーズギターの”ヘッド博士の世界塔”、その他の実験音楽的なアルバムを聴いてからいろんな音楽を聴くようになりました。
そのときは、音楽と彫刻は別々に感じていましたが、大学時代に担当教員であった野村仁先生の作品に出会い、音楽と彫刻を融合させて考えようとし始めました。野村先生は無理なく音楽と彫刻を無理なく行き来することで、音楽とも言えるし、写真作品とも言えるし、彫刻作品とも言えるような作品を発表されていました。
学生時代から幾度と彫刻と音楽を一緒にしようと試みていましたが、なかなか一緒にならなかった。無理なく一緒になりはじめたのは、2014年に生活を東京から京都に戻し、本格的に制作活動を再開させることになってからでした。美術家としての立場以外で社会と関わった経験が、作品を作るという重荷を取り除いてくれたのか、音や彫刻、平面、光、香り、天気、温度など、単位の違うものを等価に感じようとする感覚が、無理なく合わさっていくような状態でした。
久門さんは今回展示されるようなインスタレーション作品から、先ほどの「音」に関することまで、様々な分野で活躍されています。最後に、これから挑戦してみたいこと、今後の活動の展望を教えてください。
音の作品を創りたいと思っています。純粋にアルバムのフォーマットになったものを。チェルフィッチュの岡田利規さんとの演劇のときに、音の表現としてある程度の感触を感じて、それをまとめてみたい。このチャレンジはもう10年位前からずっと思っていたことです。そして、どこか、日本語が通じないレーベルからその感覚的な記録を出したい。彫刻家、美術家という視点で音だけの作品を展覧会という形式以外の方法で世界に発信していけたらと考えています。
インタビュー・編集:森詠美(インターンスタッフ)
プロフィール


